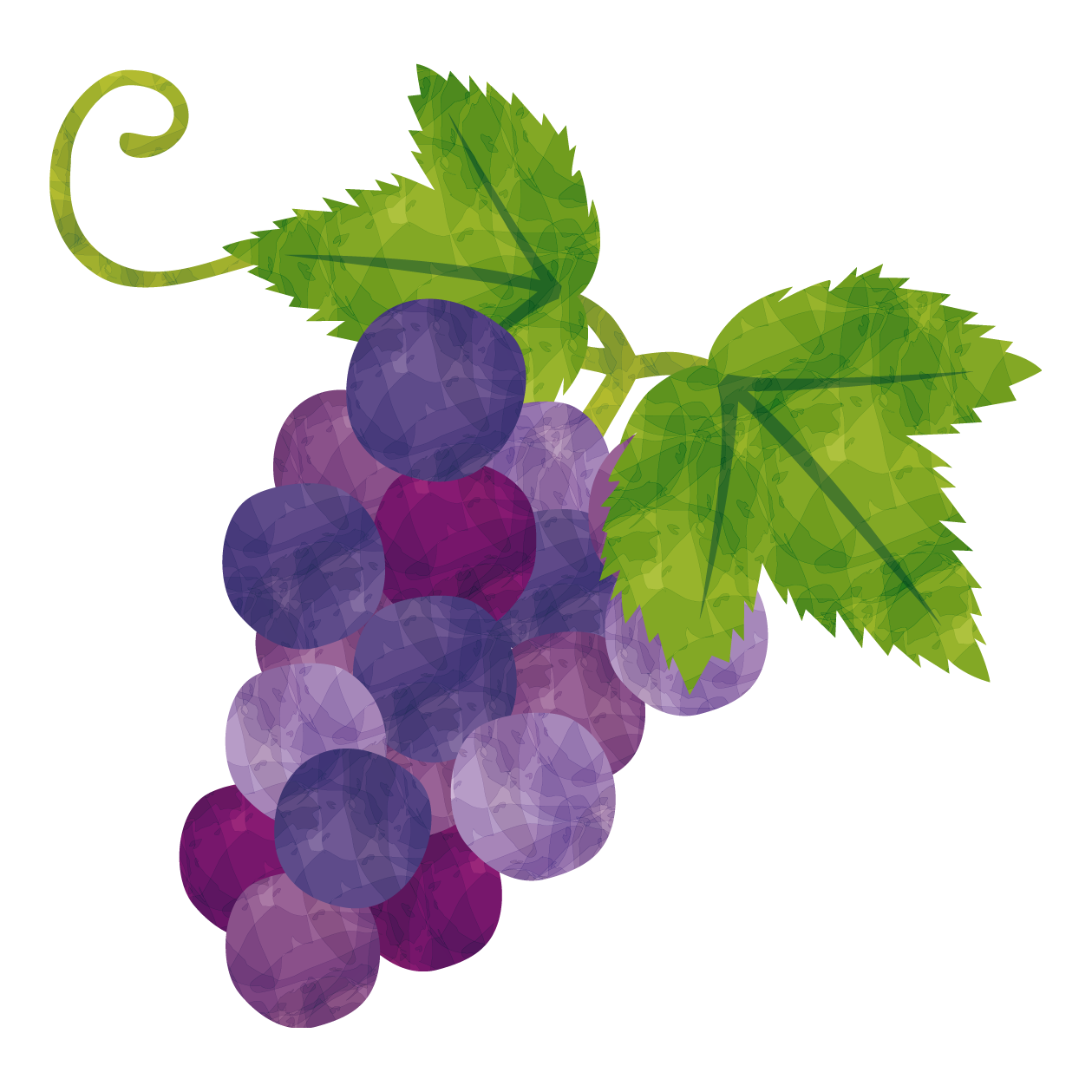ブドウ重要病害「黒とう病」 症状と対応策について

黒とう病
それは雨によって伝播する、ブドウの重要病害。
とくに雨に当たる露地栽培では、対策を行わないと、被害が甚大となります。
この記事では、近所のおっちゃんとの小話スタイルで、黒とう病の症状と対応策について紹介していきます。



うわ!ブドウの枝葉の様子がおかしい。
なんやこれ!?

あー。
これは「黒とう病」だね。

黒とう病?
黒とう病の症状
雨によって伝搬するブドウの重要病害です。
●新梢、若葉、花穂、幼果、巻きひげなど、あらゆる柔らかい緑色の部分に感染・病斑をつくり、生育を妨げる病気。
●雨によって伝搬し、4月~7月(発芽時期~梅雨明けまで)に降雨が多い年は、多発する。
●感染した枝・巻きひげにて越冬。翌年の感染源となる。
●欧州系品種は一般的に被害を受けやすいため、より注意が必要。







黒とう病の対策・予防策

「雨にあてない」これが一番!
黒とう病は雨によって伝搬するからね。
雨に当たらなければ、病気のリスクはほとんどないよ。



ビニールハウスや雨よけトンネルの設置は難しい。
そんな場合は鉢植えやプランター栽培もおススメ!
ベランダや軒下で簡易雨よけ栽培するのもありだね。

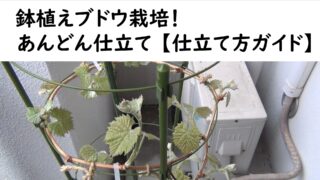



雨よけ栽培が難しい場合は、こまめな薬剤散布が大切!
黒とう病の予防は、重点防除期(感染時期)を押さえることが重要だよ!
黒とう病の重点防除期&薬剤例
①休眠期(春先):デランフロアブル
②展葉2~3枚:オンリーワンフロアブル
③展葉5~6枚:ドーシャスフロアブル
④展葉9~10枚:オーソサイド水和剤80

とくに休眠期と展葉2~3枚の防除が重要!
この時期に感染してしまうと、その後もずっと発生が続くよ!
黒とう病は若い葉っぱや枝に感染するから、芽吹いた直後は特に危険!

防除を徹底し、感染させないことが極めて大切。
「一度感染してしまった部位を元の状態に戻すことはできない」から、とにかく予防が基本だね。

こんなに薬剤散布しないといけないんか・・・

これは黒とう病に弱い「シャインマスカット」を露地栽培する場合の参考防除だから。
黒とう病に強い品種(デラウェアやスチューベンなど)なら、薬剤散布の回数を減らせると思うよ。
【品種の違いによる被害の差】は↓↓の動画を見てもらうとイメージしやすいかも!
黒とう病に感染したら

予防が大切なのは分かったが、もう感染してしまったときはどうすればいいんじゃ?

まずは、感染している枝葉を切除することが大切!
放っておくと感染部位が次の感染源となり、木全体に病気が蔓延してしまうんだ。
ここで重要なのは、切除した枝葉は必ず園地(ブドウの木)から離れた場所で処分すること!
切除した枝葉を園地の地面に投げておくと、結局、感染源となってしまうからね。


発病した枝葉を処分したら、急いで薬剤散布をしよう!
発生時期・地域によって、どの薬剤を使用するかは変わってくるから、「この薬剤を使用しておけば間違いない!」というのは少し言いにくいね。
あくまでも参考程度だけど、個人的には「オンリーワンフロアブル」を使ったりすることが多いかな。
黒とう病の恐ろしいところ

黒とう病の恐ろしいところは「感染した枝や巻きひげで病原菌が越冬。翌年の感染源となる」こと。
感染した枝は翌年の栽培では、活用することができないから、冬のせん定で黒とう病の枝は、切除&園地外で処分しないといけないね。


巻きひげも黒とう病の越冬源になるから、しっかり取り除こう!
巻きひげは冬になると、取り除くのが大変だから、春~夏の管理でちょこちょこ取り除いておくといいかも!


黒とう病は放っておくと、木全体に病気が蔓延して、終息が困難になるよ。
特に木の骨格を育成している若木の時に、感染してしまうと致命傷になるね。

黒とう病。
恐ろしい病気やな。
ブドウ栽培ガイド
ブドウ栽培に関する、その他の栽培ガイドも作っています。
ぜひ、他の栽培ガイドをご覧ください!
栽培のポイントを細かくまとめています!






ここまで読んでくれた方に、
最後におススメの書籍&おススメアイテムをご紹介!
【NHK趣味の園芸シリーズ】と【育てて楽しむシリーズ】を一緒に買えば、家庭ブドウ栽培ではほぼ困らないと思います!
初心者には
●ブドウ (NHK趣味の園芸12か月栽培ナビ)がおススメです。
より情報量が欲しいなら、
●ブドウ栽培・利用加工 (育てて楽しむ)もおススメです。

おススメアイテムはこちら↓↓からどうぞ!